(鍼、針)の効果について書きたいと思います。先回は「東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム」(ブルーバックス)という書籍を参考にしましたが、今回は一般公開されている文書を参考にします。
折りたたむ
公益社団法人日本鍼灸師会が発行している「ハリの力」に4人の医師が記事を載せられています。
「ハリの力」に、
「鍼の効果の本質―向ホメオスタシス効果」には、例えば深部体温・血圧の正常化について書かれています。
10年に及ぶ研究によると、
はり(鍼、針)をすると深部体温が高い人は体温が下がり、低い人は体温が上がる事が分かったそうです。
はり(鍼、針)が体温を正常化させるのです。
また、被験者が5000人を超える検証では、
はり(鍼、針)をすると高血圧の人は血圧が下がり、低血圧の人は血圧が上がり、正常な人は変化しないという事が分かったそうです。
この
はり(鍼、針)の力のメカニズムに関しては記述はありませんが、今後の研究に期待します。
東洋医学では「中庸(ちゅうよう)」を守る事が養生の道とされています。極端な方向に走らず、程々にバランスを整えるという事です。
血圧や体温が高過ぎず、低過ぎずになる、というのも中庸です。
この考えに沿って、私たちが日常生活で何かできないでしょうか?
養生の基本三本柱(睡眠・食事・運動)を考えてみたいと思います。
食事も同じです。食べ過ぎが体に悪い事も経験上良くない事は分かっていますし、食べなさ過ぎも又問題です。
温度も忘れてはなりません。東洋医学では冷たい食べ物や飲み物は控える事が大事といいます。では、氷を入れない常温のものだったら良いのでしょうか?東洋医学が生まれた頃、氷なんてそれ程簡単には手に入れられなかったでしょう。基準は体温です。体温より低いものはを飲食すると、お腹を冷やします。なので常温は東洋医学的には「冷たい」ものになります。もちろん熱過ぎるのも良くありません。
運動も適度な方が長続きしやすいのです。無理をして体調を悪くしたり、怪我をする事があります。功を急がず、ゆっくりとやって行くのが運動のコツです。勿論、全く体を動かさないのが大きな問題だという事も分かっています。
いずれも中庸が肝心です。
日中眠気が出ない程度の質・量の睡眠と、色々な種類の、旬の、そして出来れば地場の食材を腹八分に頂いて、程々に体を使って、元気に過ごしたいものです。
そうそう、睡眠はまだまだ解明出来ていない事が沢山あるようです。睡眠について、
筑波大学の柳沢正史教授の講話をNHKが配信しています。興味のある方は一度ご覧になっては如何でしょうか?

熱々も美味しいけど、熱さ控えめでねッ!!
いよいよ冬の寒さを感じるようになって来ました。夜中に何度も目を覚まして困るという方。お手伝いさせて頂ける事もあると思いますので、是非お近くのはりきゅう(鍼灸)院におきらくにお問い合わせ下さい。体質にあった治療によって、健康な体になるお手伝いをさせて頂きます。
折りたたむ
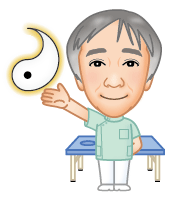 Koji Wakio(おきらく)
Koji Wakio(おきらく)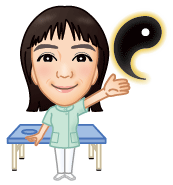 Satomi Nakano(極楽)
Satomi Nakano(極楽) 予約ご希望のお客様はこちら
予約ご希望のお客様はこちら
 メールでお問い合わせ
メールでお問い合わせ